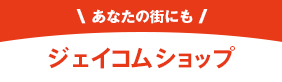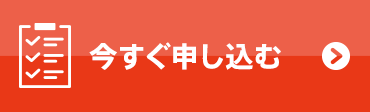第1回 気になるコラム:「ご存じですか?! 最新ネットトラブル事例」
新しい生活様式の定着で、インターネット決済はさらに加速
コロナ禍のなかで、ネット通販やオークション、フリマアプリ、さらにサブスク(サブスクリプション=定期購入)を利用する人が増えています。外出することなく、家に居ながらにして必要なものが買えるうえ、買い忘れもない。支払いでクレジットカードや携帯電話などのポイントが貯まることも、利用の後押しをしているようです。

しかし、一方でトラブルも急増しています。ネット通販に関しては、運送会社や通販会社を装い、偽サイトへ誘導したうえで個人情報を聞き出そうとしたり、遠隔操作が可能なアプリをダウンロードさせようとする迷惑メールがばら撒かれる事例が、一昨年あたりから社会的な問題となっています。昨年も被害が確認されており、犯行は継続していることがわかっていますから、引き続き十分な注意が必要です。
タイトルや本文の文字化けがあるサイトは要注意!
以下の例のように、タイトルや本文が文字化けしていたり、おかしくなっているものは、すぐに削除しましょう。「ワード」などに含まれる「ー(音引き)」や日本独自の和製漢字(国字)が化けることがほとんどですので、覚えておくと役に立つでしょう。
Amazon. co. jp にご登 のアカウント(名前、パスワ
のアカウント(名前、パスワ ド、その他
ド、その他 人情
人情 )の
)の
 お客のアカウントは制停止されています - アカウントで不なお支いが出されました。取引注文を防ぐために、人情をする必要があります。
お客のアカウントは制停止されています - アカウントで不なお支いが出されました。取引注文を防ぐために、人情をする必要があります。
発信元のアドレスは一見本物のように、巧妙に偽装されていることがあります。大手の通販会社や運送会社は、ホームページやQ&Aで注意喚起をしていますから、URLをクリックする前に送信元のアドレスが公式なものかどうか、確認する習慣をつけましょう。
コロナ禍により、昨年から急増しているのがサブスクに関する相談
相談件数は5年間で10倍に
2015年に約4100件だった相談は、昨年に4万4000件と5年間で10倍以上にも増えました。今年に入ってもトラブルの相談が寄せられており、消費者庁では特定商取引法(特商法)の違反で取り締まれるよう、法改正を視野に入れた議論を続けていると報じられているほどです。

「お試し」「初回90%オフ」などの宣伝文句に要注意
サブスクの相談の多くを占めるのは、「お試し」「初回90%オフ」などの宣伝文句にひかれて申し込んだところ、「知らないうちに長期間継続する契約になっていた」というものです。これらの相談は、一昨年の570件あまりから昨年には1100件を超えていて、巣ごもり消費が広がるなか、今年も被害が拡大していくのではないかと懸念されています。
具体的には、化粧品やサプリメントや健康食品、保存食品など、生活に密着した商品で被害が頻発しています。悪質なのは、解約しようにも連絡先がわかりにくかったり、問い合わせや解約のための電話がなかなか繋がらない、メールの返信が遅いなどと、意図的に騙そうとしているのかと疑われる節があることです。
事業者名や連絡先をチェックする習慣を
まずは、注文をする前に正式な事業者名や連絡先等を確認しましょう。ネットを経由した販売では、特商法の規定に基づいて事業者名やメール電話などの連絡先、返品に関わる条件等を明示しなければなりません。詳しい事項は消費者庁のホームページに公開されていますから、見ておくことをお勧めします。
また、事前に国民生活センターや地域の消費生活センターのサイトを確認し、最新のトラブル事例や公表されている悪質な業者名を知っておくことも被害防止に役立ちます。
7階建てのビルなのに…
なかには、連絡先の住所や電話番号、メールアドレスが実在しないことがあります。筆者が実際に調査したケースでは、「7階建のビルの8階に事務所があることになっていた」、「ワンフロアに10室しかないのに『○11号室』と表記されていた」いった事例がありました。業者の書いていること=正しいとは限りません。
特に返品については、開封していないことなどの条件(特約)がついている場合、無条件での解約ができないことがあります。返品等、各種の条件を事前に確認する習慣をつけることが最大の自衛策です。
トラブルに遭った際には、ひとりで解決しようとせずに、国民生活センターや地域の消費生活センターに相談し、専門家のアドバイスを受けましょう。

トラブルに遭った際には、ひとりで解決しようとせずに、国民生活センターや地域の消費生活センターに相談し、専門家のアドバイスを受けましょう。
- 「国民生活センター」http://www.kokusen.go.jp
- 「国民生活センター 相談、紛争解決/情報提供の受付」http://www.kokusen.go.jp/category/consult.html

1964年京都府京都市生まれ。同志社大学卒。会社員を経て、1989年より取材執筆活動 を開始。ITジャーナリスト・コメンテーターとしてITから時事問題までメディアへの出演及び寄稿・論評多数。ラジオ・企業および学術トップへのインタビュー、書評も多く手がける。専門分野は IT・最新インターネット事情。
1964年京都府京都市生まれ。同志社大学卒。会社員を経て、1989年より取材執筆活動 を開始。ITジャーナリスト・コメンテーターとしてITから時事問題までメディアへの出演及び寄稿・論評多数。ラジオ・企業および学術トップへのインタビュー、書評も多く手がける。専門分野は IT・最新インターネット事情。